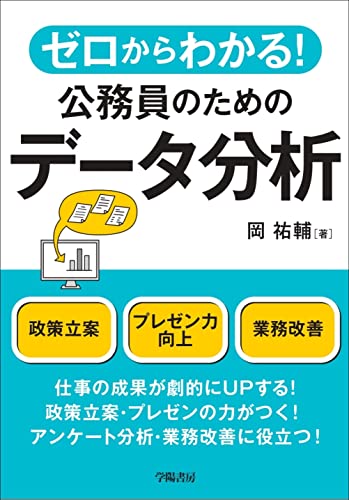ビブリオバトル再現「超合法建築」(彰国社)
ご紹介させていただくのは、「超合法建築図鑑」です。
今日、犬山の城下町を歩いて感じきましたのは、当時の為政者の考えた「まちづくり」と、現在の犬山市の方々が考えた「まちづくり」が相まって、非常に魅力的な「まち」になっているということでした。
調和の取れた「まちづくり」を目的とする都市計画法と、具体的に個別の建築物について対応する建築基準法という法律があります。
この本、法律の本じゃありません。本屋さんに行くと、建築関係の本棚にあるんですが、気になるのが「超合法」ってタイトルですね。「違法」じゃない、「合法」なんだよと。
建築行政は、規制行政ですね。規制行政は、法律で「ストライクゾーン」を明確にします。ワールド・ベースボール・クラシックでも派手な投げ合いがありましたけれど。
ということは、ストライクゾーンのギリギリを狙って投げる球もあるということですね。
この本で紹介される中で「キリン・ビル」というのがあります。「キリン・ビール」じゃない、「キリン・ビル」。キリンの首のように、ヒューっと細い躯体の上に、ちょっと大きな最上階が乗っかっている。展望台じゃない。この建物、マンションなんです。
なぜ、こんな形になったかというと、日影規制があるからというんですね。
高い建物の高い影は、お日様の動きによって早く動く。でも、低い影はなかなか動かない。要するに、建物の容積が同じであるならば、容積を高層部に振り分けた方が近隣への影響は小さくなるそうです。
何が言いたいかというと、「日影から計算されるデザインがある」ということなんですね。
他にも町中を歩いていると、マッターホルンのようにナイフで切り落とされたような建物を見ることがありますけれど、なんでそんなデザインになったかを、この本では紹介しています。
この本、「地下室マンション」についても、紹介されています。
「地下室マンション」を大学の授業で紹介したしたとき、学生に「地下室で洗濯物が乾くのかな?」と聞かれたんですね。
地下室とはいっても、地面に埋もれているわけではない。斜面の上に建設された、数階部分だけが階数としてカウントされるんですね。
この本では、「階段マンション」と紹介されています。斜面地に階段状にマンションを建設することで、高さ制限をクリアするとともに、斜面に建設された部分を地下室扱いして、容積率に算入されない。「超合法」ってやつですよ。
じゃあ、合法ならよいのか。「超合法」を許容するのかという問題ですね。住宅街に巨大建築物が突如出現したわけですから、周囲への圧迫感は大きい。
これを条例で規制したのが、神奈川県でいえば、横浜市や横須賀市などです。 このように「ストライクゾーン」が明確にされる中で、事業者さんも、役所も、「ストライクゾーン」に投げ込むというのが、現状の法律の解釈と自治体の運用としてあるんだなあ、ということです。まさしく、「超合法」の言葉の中には政策法務の意味も、込められるのではないかと思います。
私、建築行政の詳しいことはわからないんですけれど、絵を見ているだけでも楽しい本ですので、ご興味ある方は、図書館や本屋さんで手に取っていただけたらと思います。
ありがとうございました。
第27回自治体法務合同研究会 犬山大会

去る7月15日(土)から16日(日)にかけて、4年ぶりに自治体法務合同研究会がリアル開催されました。
昨年はウェブ開催され、私は関東学院大学のキャンパスから、自治体の「終活事業」について報告させていただきました。報告後は、ウェブ上で交流会も開催されましたが、やはり物足りなさは拭えず。
開催地の犬山を訪れたら、北海道から九州まで、久しぶりの方々との直接対面が嬉しく(^^)
開催に当たっては、大変なご苦労があったと思います。スタッフの皆さま、ありがとうございました。
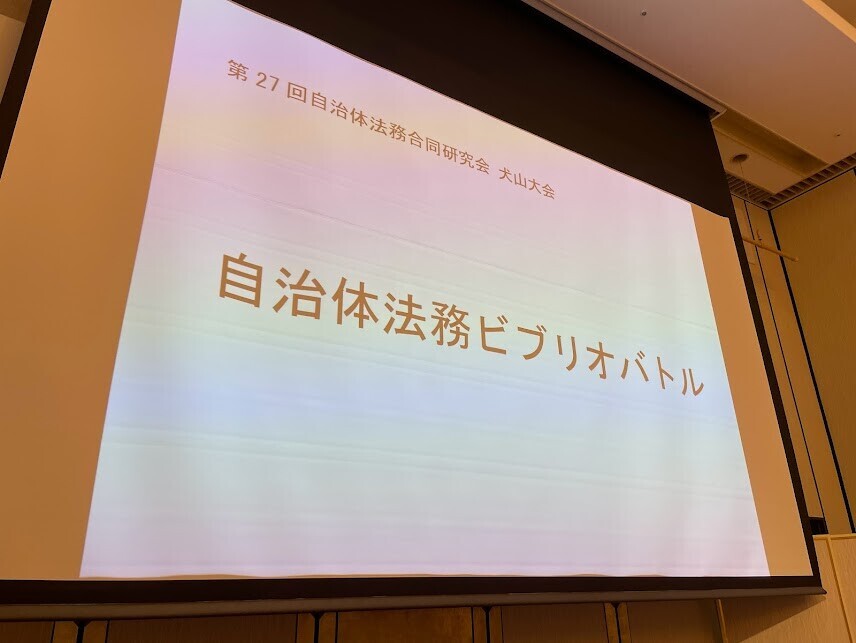
私の出番は、閉会式直前の自治体法務ビブリオバトル。
グループ対抗の中、「超合法建築図鑑」を紹介し、優勝の栄誉をいただけましたヾ(*´∀`*)ノ゛
実は、合同研究会のっビブリオバトルへの出場は2回目。前回は芳しくない結果であったことから、なんとかの雪辱です。
「法律を読む技術・学ぶ技術」改訂第4版
「自治体の教育委員会職員になったら読む本」
教育行政に橋頭保が築かれた。過言ではなく、そう思います。
市町村の教育委員会は、首長部局から独立した執行機関である一方、県費負担教員など県教育委員会の関りも大きい。
これらタテ・ヨコの行政運営の複雑さに加え、仕事場では役所で採用された「行政職員」と教員出身の「教育主事」が席を並べます。
教育行政の現場への赴任者は、行政職員であれ教育主事であれ、戸惑いは少なくないでしょう。
本書は、法律上の制度の仕組みから学校におけるトラブル対応まで幅広く説明します。政令市教育委員会の法制担当を務める著者の指摘は、実務的でわかりやすい。
教育行政に対し、住民の期待は大きいのが現状です。
円滑な業務遂行のために本書が広く活用されることを期待します。
「ゼロからわかる! 公務員のためのデータ分析」
「業務の「ヒヤリ!」を解消する!公務員の法的トラブル予防&対応BOOK」
書名に「法的トラブル」とありますが、その意味は「法に基づいて処理される紛争とその背景にある違法、不当、不適切な行為」であると著者は説明します。
住民対応や情報漏洩のほか、職員不祥事やハラスメント、交通事故など取り上げられる範囲も幅広い。近年は事例が多くなってきた審査請求や行政訴訟についても手順が丁寧に解説されています。
イラストが多く読みやすい構成なので、若い人に読んでいただけたらと思います。中堅職員やベテランの方も知識の確認にも役立つ内容です。
「イメージコンサルティング」を経験しました。
このたび、元東京都職員の古橋香織さんにイメージコンサルティングをしていただき、その顛末について執筆の機会を得ました。
記事に掲載がある「パーソナルカラー診断」は、ファッション分野で近年注目を浴びているそうです。記事では、古橋さんの新刊である「公務員男性の服」のご紹介もさせていただいています。
50代のおっさんのささやかな冒険譚をお楽しみいただけたら幸いです。
当日は診断に引き続き、私のスーツ購入にもアドバイスをいただいたのですけれど、コンサルティングの舞台裏について、古橋さんもご自身で記事を書かれています。
私自身、身なりは無頓着なところがありますので、貴重な機会でした。ご興味ある方は、併せてお読みいただくと興味深いと思います。

![元法制局キャリアが教える 法律を読む技術・学ぶ技術 [改訂第4版] 元法制局キャリアが教える 法律を読む技術・学ぶ技術 [改訂第4版]](https://m.media-amazon.com/images/I/51dCNaPiDmL._SL500_.jpg)